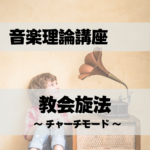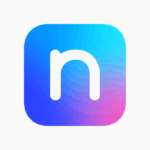みなさん、こんにちは。

五度圏ってよく出てくるけど、これは何?どうやって使うんだろ…
今回はこんな疑問を解消します。
五度圏とは
五度圏とは、5度上の音を順に並べた環(circle)で「circle of fifth(サークルオブフィフス)」と呼ばれます。全部で12ある音を元に、長調(外円)、短調(内円)で並べられています。
C→G→D→A→E→B→F#(G♭)→D♭→A♭→E♭→B♭→F→C
このように5度上の音を並べていくと12音でちょうど一周し、それぞれ長調、短調があります。単調はこんな感じでC(長調)とAm(短調)が重なるように並びます。
Am→Em→Bm→F#m(G♭m)→D♭m→A♭m→E♭m→B♭m→Fm→Cm→Gm→Dm→Am
五度圏表でできること
五度圏表を使うことで「調」や「コード」を瞬時に導くことができます。
- 「調」がわかる
- 「コード」がわかる
まずは五度圏表で調についてみていきたいと思います。調とはスケールとも言われ、調(スケール)によって曲の世界が決まります。Cの世界は基本的にドレミファソラシの7音からできているように、この7音に#や♭が付くことで世界がガラッと変わるのが音楽です。
五度圏表は、この調を理解するのにとても役立つ表なのでこれからいくつか見ていきます。
五度圏表でわかる「調」
それでは五度圏表の「調」について注目してみましょう。五度圏表の調:①平行調
まず、五度圏表を使うことで「平行調」がわかります。
平行調とは、同じ構成音からできている2つのスケール(調)でしたね。例えば、CメジャースケールとAナチュラルマイナーは平行調の関係にあります。
五度圏表を使うことで、この平行値が瞬時にわかります。五度圏表を見た時、円の中心に向かって縦に並ぶ長調と短調、これが平行調の関係になります。
五度圏表の調:②譜面の#と♭の数
五度圏表を使うことで譜面に付く「#,♭の数」がわかります。
C(メジャースケール)はドレミファソラシなので#、♭が無し。Cから時計回りに進むにつれて#の数が1つずつ増えていきます。逆に反時計回りに進むにつれて♭が1つずつ増えていきます。
この時、どの音に#(もしくは♭)が順に付くのかですが、#と♭では調号の付く順番が真逆になります。
- #が付く音の順番:ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シ
- ♭が付く音の順番:シ、ミ、ラ、レ、ソ、ド、ファ
例えば、Cメジャースケールの右隣Gメジャースケールは#1つ付くわけですが、ファだけに#がついて「ソラシドレミファ#」Gメジャースケールになります。Gのさらに右隣Dメジャースケールは「ファ」「ド」に#が付くので、Dメジャースケールは「レミファ#ソラシド#」ですね。
このように五度圏表を使うことで、調号(#、♭)がいくつ付くのかが瞬時にわかるのです。
五度圏表でわかる「コード」
ここまでは五度圏表を使うことで「調」がわかることを解説しましたが、次に五度圏表のコードに着目してみましょう。
五度圏表のコード:①進行
五度圏表を使うことで「コード進行」がわかります。
- ドミナントモーション
- ツーファイブワン
こういった進行パターンはどの曲にも出てきます。ドミナントモーション「Ⅴ7→Ⅰ」、ツーファイブワン「Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」は曲の終わりで必ずと言っていいくらいよく使われています。
隣に五度上のコードが並ぶ五度圏表では反時計回りにⅡ→Ⅴ→Ⅱとなっており、ⅡはⅤから見た五度上のコードになるため、この関係性は永遠にループします。
五度圏表のコード:②ダイアトニックコード
五度圏表を使うことで「ダイアトニックコード」がわかります。
ダイアトニックコードは曲を構成する7つのコードでスケールの7音が元になっています。
例えば、Cメジャースケールであれば「ドレミファソラシ」の7音を元に「C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5」の7つのダイアトニックコードが作られます。
- C(ドミソ)
- Dm(レファラ)
- Em(ミソシ)
- F(フアラド)
- G(ソシレフ)
- Am(ラドミ)
- Bm-5(シレファ)
五度圏表では、ここダイアトニックコードがまとまって並んでいるのがわかると思います。
五度圏表のコード:③裏コード
五度圏表を使うことで「裏コード」がわかります。
裏コードとは同じトライトンを持つコードで、ドミナントセブンスの代用として使用することができるコードです。
例えば、G7(ソシレファ)は「シ」「ファ」が6半音の間隔でトライトーンになります。この「シ」「ファ」が含まれるコードは「D♭7(レ♭ファラ♭シ)」でこれがG7の裏コードです。
五度圏表から裏コードを見つける方法は、円の対角線に書かれているコードが裏コードとなります。裏コードはⅡ♭7なんですが五度圏表を使うと裏コードも簡単にに見つけることができますね。
裏コードについては、こちらの記事で解説しています。
【音楽理論講座】代理コードとは?種類や見つけ方、ヒントは構成音に含まれるトライトーンです五度圏をYouTubeで解説
五度圏をYouTubeで解説しました。
動画の方が理解しやすいと思いますので、参考にしてみてください。