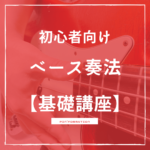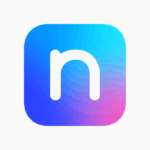ディグリーネーム(=Degree Name)って聞いたことありますか?
コード表記では必ず目にするローマ数字ですよね。
今回はそんなディグリーネームについて解説していきます。
ディグリーネーム
『ディグリー=度数』
ディグリーネームとはキーをもとに作られるスケールを数字の「度数」で表記したものです。
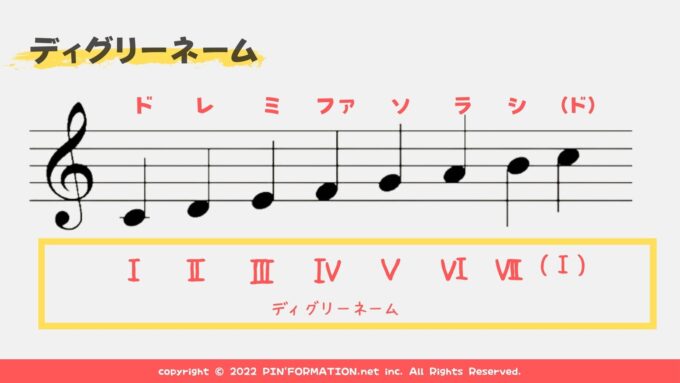
上図はC(ド)を起点に作られる、Cメジャースケールです。これは、CをⅠ(1度)として7つの音に数字をつけています。
- Keyにおけるコードの役割を把握しやすい
- 作曲や編曲の際に応用させやすい
- コード進行の引き出しをたくさんストックできる
度数表記で表すことでこのように、演奏や作曲において特定のコードを把握しやすくなります。
ルートからの距離を度数で表す
それでは度数について詳しく見てみましょう。
分かりやすく「ドレミファソラシ」というCメジャースケールの音で考えてみます。
ルートは「C(ド)」なのでこれが1度となります。レ=2度、ミ=3度、…シ=7度のように「度数」で表し8度で同じ音が登場します。(オクターブ上の音と呼びます。)
この7音は2つのグループに分類できます。完全音程と長短音程です。
【完全音程】1度、4度、5度(8度) 【長短音程】2度、3度、6度、7度
1度、4度、5度は「完全音程」と呼ばれ、頭にパーフェクトとつけて呼んだりします。たとえば完全5度のコードを「パーフェクト○○」と呼びます。
それに対して、2度、3度、6度、7度の音は
2度、3度、6度、7度の音はすべて、「長」か「短」が頭につきます。「ドレミファソラシ」の例だと、レ=長2度、ミ=長3度、ラ=長6度、シ=長7度となります。
全て「長」がつきましたが、「短」はどの音になるのか。それは黒鍵の音です。長○度の音がフラットした(半音下がった)音を短○度と言います。
この例だと、レ♭=短2度、ミ♭=短3度、ラ♭=短6度、シ♭=短7度と呼びます。
ファ#の音だけ名前がない
この時、「ファ#」だけ長短で表せない音になります。
この音は「
この音は
トライトーンについてはこちらの記事で解説してます。
ダイアトニックコード
それでは、ダイアトニックコードで考えてみましょう。
ダイアトニックコードとは、スケールの三和音のこと。
Key=C,ⅠをCとして考えます。
Cのダイアトニックコードは以下のように、ディグリーネームで表すことができます。

メジャー、マイナー
ディグリーネームで、メジャーコード、マイナーコードを区別できます。
上の例で言うと
- 「C」→『Ⅰ』
- 「F」→『Ⅳ』
- 「G」→『Ⅴ』
がメジャーコードなのです。
- 「Dm」→『Ⅱm』
- 「Em」→『Ⅲm』
- 「Am」→『Ⅵm』
- 「Bm-5」→『Ⅶm-5』
マイナーコード、フラット5などは、ローマ数字の後ろに『m』や『-5』などをつけて表記します。
4和音
ここまで3和音のディグリーネームについて見てきましたが、4和音だとどうなるか見ていきます。
3和音のときと同様に、「Key=C」のダイアトニックコードに1音足して、4和音を作ってみましょう。

4和音になると、7度の音が加わりますが、表記も『(ディグリーネーム)7』とすればOKです。
- 「C△7」→『Ⅰ△7』
- 「Dm7」→『Ⅱm7』
- 「Em7」→『Ⅲm7』
- 「F△7」→『Ⅳ△7』
- 「G7」→『Ⅴ7』
- 「Am7」→『Ⅵm7』
- 「Bm7-5」→『Ⅶm7-5』
同様に、9thや13thなどのテンションノートについてもディグリーネームで表すことができます。
まとめ
ディグリーネームを使うことで、作曲や編曲の際に、アレンジや応用ができるようになります。
コード進行を相対的に捉えられるからです。
- コード同士の繋がりや位置関係
- 「KeyのトニックⅠ」からの距離
コード進行には法則性があるため、数式にあてはめて考えられるようになります。
なので、ぜひこのディグリーネームにも慣れておくと良いでしょう!
»»Instagram【ディグリーネーム】